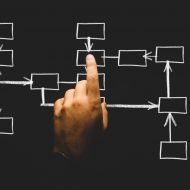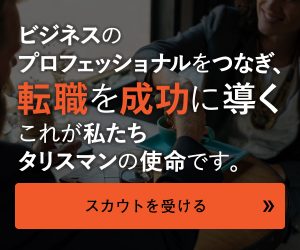みなさん「エンジニア35歳定年説」というものを聞いたことがありますか?これはIT業界で古くからいわれている俗説であり、根拠が明確なものではありません。実際にその説に対して、さまざまな意見や解釈が存在します。
この記事ではIT業界におけるエンジニア35歳定年説が囁かれる背景にある理由や、エンジニアの系統による定年説のリアリティの違いなどを解説していきましょう。
目次
35歳定年説の背景にあるものとは?
35歳定年説というのは、35歳を過ぎたエンジニアは、もう現役を続けられないといういわゆる「俗説」です。誰がいつ言いだしたかも分かりません。
1990年代後半には有名な説として語られていて、それに対する否定的な意見も多く語られました。
主に以下の3つが、エンジニア35歳定年説の要因と考えられます。
●収入を上げるための方向性が定まっているかどうか
●体力の低下
●新しいスキル習得の困難さ
そのひとつ一つを詳しく見ていきましょう。
収入を上げるための方向性が定まっているかどうか
さまざまな職種で全般的に言えることですが、35歳という年齢は管理職への門が開き始めます。10〜15年にわたる業界の経験を通して、知識や技術、ノウハウを吸収したベテランとして、後進の管理と育成ができる管理職候補が生まれる年齢だからです。
もっといえば、年齢的には家庭を持ったり子供ができたり、住宅を購入したりなど経済的な負荷がかかってくる年齢といえるでしょう。それ以前よりも高い収入が必要になってきます。
ところが、それまでやってきたのと同じようにコードを書き続けるのであれば昇給は望めないでしょう。
収入を上げるためには、エンジニアとして継続してコードを書いていたいという気持ちがあっても、それだけでは叶いません。
マネジメントをする立場=管理職になるか、より高度な専門性を持ってそれを求める企業に転職するかが、収入を上げるための現実的な選択肢です。
この2つの選択肢に、もう少し詳しく触れておきましょう。
マネジメントという選択肢
企業側もチームで大きい結果を出すために、知見の豊かな信頼できるベテランに、皆を指導する立場に移行して欲しいと考えます。
コードを書きたい思いとは別に、プライベートの利害と企業側に利害が一致する、マネジメントへの移行をとるベテランが多くなるのは自然な成り行きともいえるでしょう。
一般的にそのタイミング、つまり仕事においてスタッフを指導・管理できるレベルに達する時期と、プライベートで経済的課題に直面する時期は同じく35歳前後であることが多いのです。
管理職に就けば、コードを書く仕事よりもプロジェクトの統括がメインの役割になるので、エンジニアとして現場の業務に携わり続けるのは難しくなっていきます。
ただし大切なことは、エンジニアなら誰でもマネジメントに移行できるわけではありません。マネジメントの方向性に進むのであれば、前もってその方面に必要なビジネススキルやヒューマンスキルを磨いておく準備が必要となります。
転職という選択肢
現場のエンジニアでありつつ収入を上げるためには、誰にも負けない高い専門性を持っていたり、最先端のテクノロジーに関する深い知見を有するなどのプライオリティ(優位性)を生かして、転職によってステージアップする方法が現実的です。
しかしそのためには、エンジニアにとって転職が難しくなるとされる35歳になるまでに、それを見据えた準備を虎視眈々としていなければなりません。企業にスキルを求められて転職するレベルには、一朝一夕には到達できないからです。
こういった、マネジメントや転職というキャリアシフトの方向性を自身が見出せているかどうかが、エンジニア35歳定年説と深く関わっていると考えられます。
体力の低下
エンジニアの仕事は納期が非常に重要です。プロジェクトの進捗次第では昼も夜もなく働き続けることも珍しくはありません。また、仕事そのものがシステム設計やコーディングという、いずれも高い集中力が求められるものです。
そうであるがゆえに、技術だけではなく体力と集中力が充実している年齢でなければ務まり難いと考えられているのでしょう。
新しいスキル習得の困難さ
IT業界の革新されていくスピードは凄まじく、ついこの間まで最新と思われていた技術でも、気がつけばもう古くなっているようなことが日常茶飯事です。
そのため、エンジニアは常に新しいスキルを学び続けていかなければ、トレンドにキャッチアップできなくなり、現場に通用し難くなっていくと考えられます。
変化が見られるエンジニア35歳定年説?
最近の業界の動向として、エンジニア35歳定年説が崩れ始めている兆候があります。IT業界が人材不足に苦しむ中、スキルや知識、経験が豊富なベテランのエンジニアが現場での頼れる戦力として重宝され、ベテランニーズが高まっているのです。
また、デジタル変革が各分野で進行するに従って、スペシャリストとしての知見とノウハウを持つエンジニアは、年齢を問わず現場から求められています。
そのため、35歳を過ぎても管理職ではなくプレイヤーとしてとして働き続けるエンジニアも増えているようです。
エンジニア系統による事情の違いとは
エンジニア35歳定年説は、額面通りではないにせよ「一理ある」くらいはあるかもしれません。しかしながら、主に開発系エンジニアに関する話であり、違う系統のエンジニアにはあまり関係がないかもしれません。
それを説明する前にまず、エンジニアの種類を、大まかに整理しておきましょう。エンジニアには大きく分けると「開発系」「インフラ系」「営業系」の3つに分かれます。
そして開発系の中で極めて独自性が高いWeb関係を「Web系」として別にすると4系統です。
開発系エンジニアは、いわゆるITエンジニアの代表的なイメージを持つもので、システムやソフトウェアの開発に携わるエンジニア全般を指します。
インフラ系エンジニアとは、サーバーの管理やネットワークの構築、保守運用などを専門的に行うエンジニアです。ユーザーがシステムやサイトを通して快適にサービスを利用する背後を、インフラ系エンジニアが陰で支えています。
営業系エンジニアとは、エンジニアの知識や経験を活かして、営業やセールスに関係する活動を行うエンジニアです。
Web系エンジニアは、WebサイトやWebアプリケーションの開発から運用、保守などに携わります。Webに関する知見において、他分野のンジニアよりも高い専門性が求められるうえ、ネットワークのセキュリティに関する知識も必要です。
また、開発においてはユーザー視点のサービスを提供しなければ技術を活かすことができません。そのため、マーケティングに関する知識も求められます。
エンジニア35歳定年説が生まれた背景には、主に開発系エンジニアのようにマネジメントをする立場になるか、他の人材では賄えないプライオリティ(優位性)を武器に転職をしないと現場のエンジニアのままでは収入を増やしにくいという事情がるのです。
インフラ系や営業系はそれ自体が特化した形態なので、35歳定年説とはあまり関係がないでしょう。
そしてWeb系エンジニアは、開発系に含むことができるとはいえ、そのストーリーは異なります。なぜならWeb系企業は、元々できあがっている有能な人材で成り立っている場合が多いのです。
今後においては成熟したWeb系企業が、若手のエンジニアを増やしてチームとしてさらに成長させるためのマネジメントが必要になることでしょう。
そうなった時に、Web系エンジニアにも35歳定年説がささやかれる可能性があるかもしれません。
35歳はエンジニア人生のターニングポイント!
ここまでの考察から考えると、エンジニア35歳定年説に関してのひとまずの総括ができます。
つまり、35歳は実際の定年ではないけれど、現場の第一線からマネジメントの立場に変わるという典型的な流れを踏まえると、当たらずといえども遠からずという認識が妥当でしょう。
エンジニアにとっての35歳は、決してネガティブに考える必要はありません。むしろエンジニアにとって35歳という年齢はエンジニア人生においての大いなるターニングポイントであると、ポジティブに捉えればよいのではないでしょうか。
一般的には、仕事をしていると30代の半ば頃から、以下のような岐路に立つことがあります。
●結婚をするorしない
●子供を作るor作らない
●転職をするorしない
●マイホームを持つor持たない
他にもいろいろと考えられますが、要するに人生における重要な選択が、目の前に突きつけられるのです。30代前半では、まだまだ余裕を持って仕事に没入していた人も、後半に差し掛かると40代の迎え方を多少意識するようになります。
エンジニアに話を戻すと、前述のようにマネジメントの立場になるか、他者に置き換えができない高い専門性を持って転職する場合は、エンジニア35歳定年説は真っ向から否定してよいでしょう。
そのどちらでもない場合は35歳を過ぎて転職は難しくなります。減給のリスクも負いながら現場のエンジニアを続けるのならよいとしても、より高い収入や活躍の舞台を求めるのであれば、早い段階で自身の方向性を見出して備えておくことが大切になるのです。
エンジニアを長く続けるために気をつけておきたい4つのこと
長くエンジニアを続けるためには、いくつかの注意点があります。ここからは、それを具体的にご紹介しておきましょう。
若さというアドバンテージを補う「セルフブランディング」
35歳を超えたら、若さというアドバンテージがなくなる分、それを補う何か自分のプライオリティを持つことを意識しましょう。具体的には「セルフブランディング」です。この点では誰にも負けないというものを持ちましょう。
35歳以上のエンジニアが、能力や向上心において劣ってくるというようなことは、一般論としてはいえません。35歳を過ぎても、能力が上がる人も向上する意欲をさらに持つ人もいくらでもいます。
そのうえで、若い方が有利という面は否めません。若ければ多少の失敗は許容してもらえて、やり直しが効くでしょう。若いと徹夜も平気です。
若いというだけで多少スキルが未熟でもよくしてくれるクライアントから仕事がもらえたり、可愛がってもらえたりもするでしょう。また、勉強をするにしても独身であれば時間も作りやすく、夜更かししての勉強もできます。
つまり、記憶力や理解力などは35歳を過ぎたからとないえ、それほど変わらないのかも知れませんが、実際に勉強に充てることができる時間は、若いうちの方が圧倒的に多いでしょう。
その若さのアドバンテージを補えるセルフブランディングができれば、年齢をあまり気にせずに、減給のリスクを避けながらエンジニアを続けられる可能性があります。ただし、昇給は難しいかもしれません。
新しいスキルにキャッチアップ
実際にエンジニアが天職だと感じている人や、シンプルにコードを書くのが楽しいという人が、定年(35歳ではなく本当の定年)までエンジニアとして働き続けたいと考えるのも自然なことです。
定年まで現場に求められて仕事ができるエンジニアであるためには、培ってきたスキルのブラッシュアップに加え、新しいスキルもどんどん身につけて守備範囲を広げることが重要なポイントとなります。
自分にとって扱っていなかったプログラミング言語に挑戦してみるのも、よいでしょう。
Web系エンジニアは周辺知識があるとプラス!
Web系エンジニアに関していえば、マーケティングやSEOなどの周辺の知識を学ぶことは仕事を続ける上でプラスになるはずです。
独学でも問題ないでしょうが、スクールに通うと質疑応答もできて効率よく理解を深められる可能性があります。最近ではオンラインスクールも増えているので、学びやすい環境になっているといえるでしょう。
セミナー・勉強会・交流会に参加
エンジニア対象のセミナー・勉強会・交流会に関しては様々な意見があり、中には効果を疑問視する意見もあります。しかし、長くエンジニアを続けるための行動の一環としては、参加する価値があるといえるでしょう。
なぜなら、セミナー・勉強会・交流会には多種多様な業界の人たちが参加しているので、これまで知らなかったような新しい情報、あるいは異業種で求められているスキルが何かなどを知ることができるからです。
エンジニアの仕事は日がな一日オフィスで過ごすことが多く、人間関係も職場の中に限定されてしまいがちなのは否めません。
人脈が広がれば新しい情報を得ることもでき、コミュニケーションスキルもアップするので、セミナー・勉強会・交流会に積極的に参加することは意義があるといえるでしょう。
フリーランスという選択肢
エンジニアとして長く働き続けたい人にとって、フリーランスとしてエンジニアの仕事を請け負っていくことも選択肢のひとつになるでしょう。
会社員とフリーランスでは、主に以下のような違いがあります。
●自分で仕事が選べる
●収入が増える可能性が高い
●収入が不安定になるリスクがある
●エンジニア以外の業務も自分でこなす
もう少し詳しく触れておきましょう。
自分で仕事が選べる
会社勤めのエンジニアは、上から与えられた仕事を粛々と進めなくてはなりません。しかし、フリーランスの場合は与えられるものではなく、自分で仕事を選んで請負います。
報酬の面でも選べますが、それ以上に挑戦してみたい仕事やキャリアアップにつながる仕事を選べば、エンジニアとしての将来に反映することができるのです。
収入が増える可能性が高い
フリーランスエンジニアは、在宅でコードを書くだけでなく常駐して行う業務もあればプロジェクトのマネジメントなど、いろいろな仕事があります。
総合的には、フリーランスエンジニアは、会社勤めのエンジニアよりも高い収入になるというのが定説です。
ただし、そこから年金や保険などの費用を賄わなくてはなりません。余裕をもって会社勤めの時の1.5倍程度の収入を獲得できるように受注するプランを立てることが望まれます。
収入が不安定になるリスクがある
会社勤めであれば、給与が確実に毎月振り込まれます。しかし、フリーランスは自分で営業をして仕事をとってこなければ、稼ぎにはなりません。
働いた時間に関係なく、納品した成果物で報酬が支払われるので、月によって多い少ないがあります。そもそも、固定的に毎月の報酬が安定しているというわけではありません。
フリーランスエンジニアとしてのキャリアを歩む場合は、ある程度の収入が確保できる目処をつけておく必要があります。
エンジニア以外の業務も自分でこなす
会社勤めなら基本的に与えられた仕事だけをすればよいですが、フリーランスの場合はそうはいきません。エンジニアとしての仕事以外に、そもそも仕事を取る営業や帳簿付け、保険や税金に関する事務なども自分で行わなくてはならないのです。
収益が出てくれば会計士や税理士といった士業の先生に任せればよいのですが、なかなかそうもいきません。しかし、最近では会計のWebサービスもあるのでそういうものを利用するのもひとつの方法です。
まとめ
エンジニアの人材不足が続く限りは、経験豊富なベテランエンジニアが現場で重宝されることもあります。もちろん、それでも、若手のニーズの方が多いのは事実です。
開発系を中心として、エンジニアが35歳を過ぎて満足な収入と活躍の場を確保するためには、遅くとも30歳を過ぎた頃から自分の将来のビジョンを考えて準備を始めることが望ましいでしょう。
マネジメントの方向に進むのか、より高い専門性を持つプロフェッショナルとして転職するのかによって、身につけるべきスキルも変わってきます。30代に差しかかるエンジニアのみなさんは、35歳以降を真摯に見据えて準備を怠りなく進んでください。