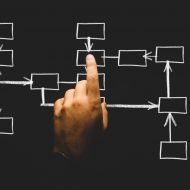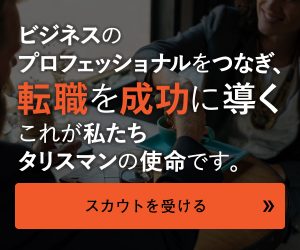一般的に、転職や退職に相応しい時期は12月と3月とされることが多いようです。年末や年度末というキリがよい時期にあたり、人事異動や入社の時期とも重なるので、退職のタイミングとしても選ばれやすいのでしょう。
しかし、実は退職のタイミングは12月か3月がベストだとは限りません。タイミングによっては、大きく損をしたりリスクを抱えることもあります。退職時期を決める上で、自分の取り組んでいる案件の進捗やその企業や部署の繁忙期などの個別の事情以外に、大きなポイントがあります。
この記事では、円満退職を目指すうえで、退職を切り出す「ベストなタイミング」から、「具体的な伝え方(例文付き)」までを徹底解説します。この記事を読めば、自信をもって退職交渉に臨めるようになるでしょう。
目次
退職を切り出すベストタイミングはいつ?【法律・会社ルール】
まずは、退職を伝える際のルールから確認していきましょう。法律と会社の就業規則、両方の側面から見ていくことが重要です。
法律上のルール:民法では「2週間前」
民法第627条では、雇用期間の定めのない正社員の場合、「退職の申し入れから2週間で雇用契約が終了する」と定められています。
つまり、極端な話、法律上は退職希望日の2週間前までに伝えれば問題ありません。しかし、これはあくまで法律上の最低限のルールです。円満退職を目指すなら、就業規則や会社の慣習を考慮する必要があります。
会社のルール:就業規則の確認
多くの会社では、就業規則に「退職希望日の1ヶ月前までに申し出ること」といった規定が設けられています。この場合、民法が優先されるため、就業規則は法的な拘束力を持たないと考える人もいます。しかし、会社との不要なトラブルを避けるためにも、まずは就業規則に則って退職を申し出るのが賢明です。
理想的なのは、退職希望日の1~2ヶ月前に伝えること。後任者の選定や引き継ぎ期間を十分に確保することで、会社に迷惑をかけずに円満に退職できます。
なぜなら、退職する場合は業務の引き継ぎや取引先への後任者の顔つなぎなどが必要になるからです。それらを無視して自分の都合で退職しようとすると、トラブルの原因になります。かといって、すべてが丸く収まるには、退職意向を告げてから1ヶ月以内では短く、2ヶ月を超えると長過ぎてしまいます。次に転職が決まっている場合は、入社まで長い期間を待ってもらえません。
これらを考慮し、退職は1~2ヶ月前までに伝えた方が良いでしょう。
状況別のベストタイミングは?「ボーナス後」と「繁忙期」
理想的なタイミングは理解したが、状況別の最適なタイミングはいつなのでしょうか?
ボーナスをもらってから退職したい!
「ボーナスをもらってから辞めたい」と考えるのは自然なことです。会社に貢献した対価として、正当なボーナスを受け取る権利はあります。
多くの会社では、ボーナス支給日に在籍していれば支給対象となります。そのため、退職を切り出すのはボーナス支給日の翌日がベストなタイミングです。ただし、なかには「退職の意思を伝えた時点でボーナスは支給しない」といった規定を設けている会社もあります。確実にもらうためにも、退職を切り出す前に必ず就業規則を確認しておきましょう。
夏のボーナスをもらって退職する場合の問題点
夏のボーナスをもらって退職する場合は、6月末や7月末に退職意向を伝えて、8月末や9月末に退職することになります。しかし求人の前半のピークともいえる3月に転職活動を行って4月ごろに内定が出ていると、就業まで期間が空き過ぎるという問題が出てしまうでしょう。
だからといって、ボーナス時期から逆算して5月に転職活動の照準を合わせても、求人の谷にあたるので「良い求人に巡り合える確率」という観点では不利になることも。つまり、夏のボーナスと3月の求人ピーク時期での活動との両方を享受するのは少し難しいかもしれません。
もちろん、その場合は転職の成功を優先するべきです。場合によっては夏のボーナス時期よりも早く退職することも、いたしかたありません。
また、注意点として3月は多くの企業が欠員補充のための求人を出しますが、同時に人事部門が得に忙しい時期です。そのため面接日程が組まれにくかったり選考が進みにくかったりなどで、活動のリズムが悪くなるおそれもあります。一概にはいえませんが以上のような事情を考慮すると、ここから先に述べるように冬のボーナスをもらってやめるほうが何かと都合が良い可能性があります。
冬のボーナスをもらって退職するのが理想的な場合も
冬のボーナスをもらって退職する場合は、12月中頃〜末に退職意向を伝えて、1月末〜2月前半に退職することになります。これであれば、後半の求人ピークである10月に照準を合わせて活動できます。また人事部が多忙な3月よりも、活動が進みやすい傾向にあります。そして、11月中に内定が出ればボーナスをもらってからの退職スケジュールによって2月入社が可能になり、待たせ過ぎにはなりません。
つまり、すべての事情を考慮すると、10月の転職活動照準を合わせて翌年の1月〜2月退職というタイミングが理想的になります。もちろん、必ずしも内定がそういうタイミングで出る保証はありませんが、おおまかなスケジュールを考える上では目安としておすすめです。
繁忙期は避けるべき?
会社の繁忙期は、上司や同僚が多忙を極めるため、退職の話をするタイミングとしてはあまり望ましくありません。
繁忙期に退職を切り出すと、会社に大きな負担をかけてしまうため、円満退職が難しくなる可能性があります。会社や同僚の迷惑を考え、繁忙期を避けて落ち着いた時期に伝えるのが理想的です。
超重要!退職を切り出す前にやるべき「5つの準備」チェックリスト
退職を切り出す前に、必ず以下の準備を済ませておきましょう。
- 就業規則の確認: 退職の申し出期間や有給休暇のルールを確認します。
- 引き継ぎ業務の整理: 担当業務の一覧やマニュアルを作成し、引き継ぎ準備を進めます。
- 有給休暇の残日数確認: 退職日までのスケジュールを組むために、残りの有給休暇を確認します。
- 転職先との入社日調整: 転職先の担当者と入社日を調整し、退職交渉をスムーズに進めます。
- 退職の意思を固める: 上司に引き止められた場合でも、意思が揺るがないように、退職理由を明確にしておきましょう。
どこで、誰に、どう伝える?「円満退職」のための伝え方
いよいよ退職を切り出す段階です。伝え方一つで、その後の人間関係が大きく変わるため、慎重に行動しましょう。
最初に伝えるのは「直属の上司」
退職の意思は、必ず直属の上司に最初に伝えます。同僚や他の部署の人に先に話してしまうと、「なぜ自分に最初に言ってくれなかったのか」と上司との信頼関係にヒビが入る原因にもなり、上司が円満退職に非協力的になるケースも考えられます。
伝えるべき場所・シチュエーション
オフィスでいきなり話を切り出すのはNGです。周りに人がいない会議室や面談室など、個室で話す時間を設けてもらいましょう。
まず、「お忙しいところ恐縮ですが、今後のキャリアについてご相談させていただきたいことがあり、少しお時間をいただけないでしょうか」とアポイントを取るのがスマートです。
【状況別】退職を切り出すときの伝え方と例文
ここでは、退職を切り出す際の具体的な例文を紹介します。
【例文1】相談の形で切り出す場合
「〇〇さん、お忙しいところ申し訳ございません。実は、今後のキャリアについて考えた結果、退職させていただきたく、ご相談のお時間をいただければと思いまして…」
👉この伝え方は、上司に相談する姿勢を見せることで、話を聞いてもらいやすくなります。
【例文2】退職の意思が固まっていることを明確に伝える場合
「〇〇さん、お時間をいただきありがとうございます。本日は、かねてより検討しておりました一身上の都合により、〇月末で退職させていただきたく、ご報告に参りました」
👉すでに意思が固まっていることを明確に伝え、引き止められた場合でもスムーズに話を進めたいときに有効です。
【Q&A】退職を切り出すときによくある疑問
- Q1. リモートワークの場合、退職はどのように切り出す?
- リモートワークの場合でも、基本は対面での対話が理想です。まずはチャットやメールで上司にアポイントを取り、オンライン面談で退職の意思を伝えましょう。
-
【メールでのアポイント例文】
件名:ご相談のお願い
本文:〇〇様
お疲れ様です。〇〇です。
今後のキャリアについて、ご相談させていただきたいことがございます。つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、〇日以降で30分ほどお時間をいただけないでしょうか。オンラインでの面談を希望いたします。 - Q2. 上司に引き止められたらどうすればいい?
- 引き止められることはよくあります。大切なのは、感謝の気持ちを伝えつつも、退職の意思を明確に伝えることです。
「大変ありがたいお言葉ですが、すでに気持ちは固まっており、申し訳ございません」と伝え、具体的な退職理由(ポジティブな理由が望ましい)を簡潔に話すと良いでしょう。 - Q3. ハラスメントが原因で退職する場合、どう伝えるべき?
- 以下のような状況では、退職代行サービスの利用も選択肢の一つであることを知っておきましょう。
・上司が高圧的で、直接話すのが怖い
・何度伝えても退職を受け入れてもらえない
・体調不良などで、会社に行けない
内定が出るまで退職を切り出すべきでない理由とリスク
内定が出るまでは、勤務先に退職の意向を切り出すべきではない理由は以下のように2つあります。
理由1:引き止めにあう可能性があるから
理由2:退職時にまだ活動中だと生活が逼迫するから
それぞれを詳しく見ていきましょう。
理由1:引き止めにあう可能性があるから
よくあることですが、企業にとってその人が今抜けられると具合が悪い場合に、引き止めされるおそれがあります。
もちろん、(上司・同僚が)あなたのことを思って引き止めているケースもあるかもしれません。しかし当のあなたは、何度もよく考えた上で結論を出しているので「はいそうですね」とはいきません。内定が出て次が確定しているなら、何があっても動じることはありません。しかし次が決まっていないとなれば、企業側もあの手この手で懐柔策を提案してくる可能性があります。たとえば給与をアップするとか昇進をチラつかせるなどです。心情的にも上司から強く引きとめられると、内定が出ていなければ後戻りする気持ちが生じないとも限りません。
しかし、残念ながらそういう流れで出てくる給与のアップ や昇進は、企業としては一番簡単にできることであり、何らかの理由でまた戻されるリスクがあります。また、口約束の場合はうやむやにされるリスクは高いでしょう。そういうことを考慮すれば、退職意向を伝えるのは内定が出るまでしない方が賢明です。
理由2:退職時にまだ転職活動中だと生活が逼迫するから
働きながら転職活動を行う中で、ある程度の手応えや見込みで内定が出る前に退職意向を切り出す人がいます。しかし、退職時点でもまだ次が決まっていないおそれのある道を選ぶのはとても危険です。よほど生活資金の備蓄があるとか、仕事の状況的に退職しなければ転職活動がどうしてもできない場合はやむを得ませんが、基本的にはおすすめできません。
いわゆる自己都合退職の場合、失業給付金の支給には2ヶ月の制限期間があるので、すぐには受け取れない上に、ハローワークにて煩雑な手続きや就職活動の認定があります。そうした負担が増える中での転職活動の長期化は精神的にも追い込まれ、苦しさから当初掲げた理想から妥協をしたくもなるでしょう。そういった理由から転職活動自体が不本意な結果になる場合もあるので、よほどの理由がないかぎり、内定が出てから退職意向を伝えるようにしましょう。
次の就業まで期間がある場合の社会保険の注意点
また、退職して次の就業までの離職期間は、社会保険を国民健康保険に切り替えるか全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続料のどちらかを選択します。国民年金の保険料も含めて、いずれにしても全額自己負担です。生活資金が逼迫する中での保険料も、見過ごせない負担になってくる可能性があります。
転職活動には有利な時期がある!
転職活動には有利な時期と不利な時期があります。それは求人が旺盛な時期とそうでない時期があるということです。詳しく解説しましょう。
転職活動に有利な時期とは?
求人が多い時期に転職活動を行えるよう、転職活動と退職のスケジュールを組みましょう。最近の10年ほどの傾向を見れば、年間に求人が増える大きな山が2回あります。それは3月と10月です。
3月に関しては年度末で退職者が多いことや、人事異動を行いポジションが空くためです。10月は年度の上半期が終わり、下半期の目標達成のために人材強化をしたい企業が動き出すためや、夏のボーナス後に退職した社員の補填のため、あるいは3月と同じく人事異動が増える時期だからです。
転職活動開始から内定までの目安
転職活動を開始してから内定が出るまでは、当然個々のケースで異なりますが、平均的におおむね1~3ヶ月と言われています。企業の選考は書類選考に始まり、面接も1次面接だけで終わることはあまりなく、2次や3次、最終面接など複数回あるでしょう。多いところでは6〜8回面接するケースもあります。
これは候補者と企業がお互いの予定を調整しながら行うためです。さらに、候補者は複数の企業を受ける場合もあるので、トータルとして1~3ヶ月かかる結果となっています。
転職活動開始から退職日までの目安
先に述べたように、内定が出てから勤務先に退職意向を告げるとしましょう。そして、これも先に述べたとおり、退職意向を告げてから退職日までに1〜2ヶ月くらいを要します。つまり、転職活動開始から内定が出るまでに1~3ヶ月、それから退職意向を伝えて退職日まで1〜2ヶ月なので、転職活動開始を起点に退職までの期間はおおむね3〜4ヶ月くらいを目安と考えればよいでしょう。
まとめ
退職時期を決める上での大きなポイントとしての、内定が出ていることや転職活動とのかねあい、ボーナスの支給などについて、注意点とともに詳しく解説しました。実際の転職においては個々の転職志望者の背景やその時の社会環境などもあって、これが正解というものは決められません。
円満退職のためには、事前の準備とタイミング、そして伝え方が非常に重要です。
- 理想的なタイミングは1〜2ヶ月前
- 会社の就業規則を確認する
- 事前に引き継ぎの準備をしっかり行う
- 直属の上司に、個室で丁寧に伝える
円満に退職するためには、最後まで真摯に業務に取り組むことが必要です。
上司に退職を切り出してから退職する当日を迎えるまでは、企業の一員にほかなりません。退職日が近くなると気が緩みがちですが、退職によってかけてしまう企業への負担をできるだけ抑えることを考え、誠意と社会人としての良識を忘れず勤め上げましょう。
![]() -メディア運営・監修-
-メディア運営・監修-
Talisman Corporation / IT・外資の転職はタリスマン
外資系企業や日系大手、ベンチャー企業への転職にご興味のある方はぜひお問い合わせください。転職エージェントとして10年以上の経験、データを持つ弊社タリスマン株式会社がサポートさせていただきます。[厚生労働大臣許可番号] 01-ユ-300282