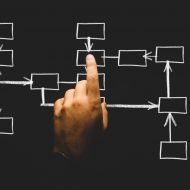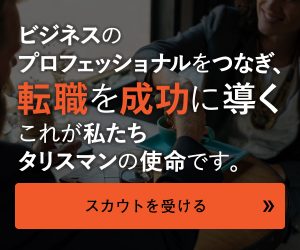企業の中間管理職というポジションについて一般的によくいわれるのは、上からの締め付けと下からの突き上げの板挟みになるということがあります。
また「責任は重いけれどそれに見合う報酬にはまだ届かない」ともいわれており、いずれにせよつらい立場であることは間違いありません。
中間管理職の具体的なつらさの理由とはどういうものでしょうか。また、その解決法はどういったことが考えられるのでしょう。
この記事では中間管理職のつらさの根本を探り、その解決策をご紹介してます。、さらに多国籍企業に関心がある35ishの読者のみなさんに向けて、つらさがお大きく緩和される外資系企業の中間管理職についても解説します。
目次
中間管理職とはどんなポジションなのか?
「つらい」とよくいわれる中間管理職ですが、その具体的な理由を掘り下げる前に、まず中間管理職というポジションはどういうものかを確認しておきましょう。
係長職
中間管理職というものは「係長」と「課長」を指すことがほとんどです。係長はその下に「主任」などのリーダー的役割や平社員を管理する役職になります。もっとも現場に近い役職といえるでしょう。
しかし、いわゆる「管理職」とされるのは「課長」と「部長」とされます。つまり係長は「中間管理職」であっても「管理職」ではないという微妙な立場です。係長は年齢的には若い人も多く、早い人は20代でも任命されることがあります。
係長から上の役職は人数も絞られるので、順調に昇進してゆくためには、まずは係長職に任命されることがスタートラインと考えてよいでしょう。
課長職
課長は堂々と「管理職」であり、まだ上に「部長」が控えているので「中間管理職」でもあります。ちなみに「部長」になると、上位者である「専務」や「常務」などはいても中間管理職ではありません。
ややこしいですが、そのような組織のフォーマットが日本企業に根付いています。
課長は非常に重要な立場であり、従業員側でもある係長と会社側の部長との間のパイプ役です。上層部の意向を現場に円滑に伝えなければならない、企業組織にとって必要不可欠なポジションといえるでしょう。
経験も必要なことから、それなりの年齢であることも条件となってきます。よって、課長職に就くのは30〜40代のビジネスパーソンが多いようです。
なぜ中間管理職はつらいのか
中間管理職とは何かを確認したところで、いよいよその「つらさ」の具体的な理由に迫っていきましょう。
責任がのしかかる割に年収は高くない
中間管理職になると当然ですが、担当部署の業績に対する責任が重くなります。また、担当する業務の量が増えますが、かといってさしたる発言権もなく、年収も満足するほど高くはありません。
結果としての「数字」を出すことだけを会社から徹底的に求められ、達成が危うければ厳しく詰められるようになります。
上位者との関からの理不尽な圧力
係
中間管理職は上位者からの強い圧力を受けがちです。時として現場を知らない上位者からの、理不尽な叱責につらい思いをすることもあります。
厄介な仕事を突然振られたり、すでに先方と揉めている案件をそのまま渡されたりと、組織にありがちな理不尽を味わうこともしばしばでしょう。上位者にとっての都合のいい部下になってしまい、そのせいでストレスを感じる人も多いのです。
それがパワーハラスメントに近づくと、場合によってはメンタルヘルスに支障をきたして、長期休職するケースも見受けられます。程度が重い場合は、退職を余儀なくされるという場合もあるのです。
部下との関係が難しい
中間管理職は、予算や目標達成のために、部下に厳しい指導をせざるをえない立場です。中にはモチベーションの低い部下や、その業務に向いていなくて生産性が低い部下もいます。
それでも彼らに成果を上げさせて、担当部署としての成果を示すことを会社から求められるのです。
一方で、現場の事情も熟知していて部下の気持ちも理解できるので、心から厳しく言うことがためらわれます。あるいは、部下から不満な態度や反抗的な言動を取られて、対応に苦しむことも多いようです。
また、今の時代は一人ひとりの部下の仕事に対する価値観も実に多様です。そして世代ごとにも大きい価値観の違いもあります。それを踏まえたうえでの、部署内のモチベーションの維持や関係性の調整という役割なので、中間管理職は大変です。
さらには、どれほど熱心に指導をしたとしても、必ずしも成果につながらないこともあり、もどかしさもストレスの増加を助長します。
昇進のスピードが遅い
年功序列の名残が完全には消えない中で、中間管理職が腫れて管理職になるには、成果を出しても簡単にはいきません。ポストが空くまで待ち続けなければならないのです。
プライベート、家庭内でも問題が出やすい
年代
中間管理職の当たる年齢の30〜40代は、会社のことだけではなく各人の家庭においても、さまざまな問題が出てきやすい頃です。子供が思春期を迎え難しい年頃であったり、受験を控えていたりもするでしょう。
あるいは親の介護が必要になったりして、難しい対応を迫られることもあるかもしれません。
悪くすると会社でも孤立していて、本来気が休まる家庭の中にも自分の居場所がないように感じられる状況も起こり得ます。
さらにいえば、体力が徐々に衰えはじめる年代でもあるので、心身ともに疲れ果ててしまうのです。つまり、仕事でのストレスだけではなく、家庭でのストレスや自身の体力の衰えからも、メンタルヘルスの不調につながるおそれがあります。
つらさを解決する方法
ここまで見てきたように、つらい立場である中間管理職ですが、そのつらさを解決、あるいは緩和する方法がないわけではありません。完全なる特効薬などはありませんが、参考までに少しでも効果がありそうなものを、3項目ほどご紹介しておきましょう。
マネジメントに徹する
本来、中間管理職は部署内のマネジメントさえ行っていれば、それでよしとされてきました。企業によっての違いはあるにせよ、昨今では中間管理職であっても、マネジメントはもちろんのこと、実務もこなさなければならない傾向にあります。
自身でこなす限界を超えている量の実務であれば、本来は部下に任せるものです。しかし、任せるためには適切な指導や引継ぎをしなければなりません。
実際には、そんな時間さえも作れないほどの多忙さに追いかけられることもあるようです。結局実務の多くもひとりで抱え込んで、マネジメントに加えてあれやこれやの仕事に追われることになります。
その結果心身に悪影響が出てくるので、ひとりで抱え込むことは負のスパイラルに入ってゆくだけです。
そういう状況においては、徹底してマネジメントに専念し、それ以外の仕事は一切しないというスタンスを貫くことが活路となり得ます。
それで生まれる余裕をもって、一人ひとりの部下に丁寧に指導して、チームで全体の仕事を手分けしてこなす方向に持っていくという、マネジメントの基本に戻ることがもっともよい対応策と考えられるでしょう。
ついつい目の前の忙しさから自分でやってしまおうという気持ちを抑え、面倒臭くても部下を上手にマネジメントすることに時間をかければ、改善しだした時のスピード感が全く違います。
ある例え話がこの解決法をうまく表現しています。ご存知かもしれませんが参考までにご紹介しておきましょう。貧しくて飢えた少年を助けてあげるのに、魚を与えるか、魚の釣り方を教えてあげるかという話です。
魚を与えるのは、あくまでその場しのぎとしてその日の飢えをしのぐ効果しかありません。明日にもまた彼は飢えてしまいます。かといって毎日魚を与えるのは自分も大変です。
一方、魚の釣り方を教えてあげれば、その後少年は独力で魚を釣って、日々飢えをしのぐことができます。さらには自分が食べ切れなくて余った魚を、人に売るという経済行為も可能となります。
面倒であっても自己完結させることを丁寧に指導すれば、その後の展開がダイナミックになるということ示した例え話です。この話は、部下に対して丁寧に根気よく指導をすることの見返りが、必ずあると教えてくれています。
部下との良好な関係を構築するヒント
部下と接する時に、ともすれば忘れがちな、自分自身が彼らのように新入社員であった頃の気持ちを思い出してみることは案外効果的です。誰しもそんな頃は、仕事がこなせないことに焦りや不安、ともすれば悔しさも感じていたのではないでしょうか。
一旦その視点に戻ると、同じことでも伝え方が変わることがあります。部下にとってより理解しやすい指導がなされれば、徐々に部署の運営も円滑化してゆくはずです。
もちろん、部下が怠けていたり、報告が抜けていたり間違いがあったりした場合には、厳しく叱責しながら指導をしなければなりません。
ここで、部下への叱責や厳しい指導がパワーハラスメントにとられないかと心配していると、部下を指導すること自体がストレスになってしまいます。
誰しも叱責されたり厳しい言葉をいわれたりは良い気はしません。しかしながら、日頃から良好なコミュニケーションが取れていれば、そうでない場合に比べて嫌悪感は緩和されるものです。
日頃から部下と真摯に向き合って、信頼関係を築いておけば、指導のストレスも減らすことができます。
変革できることとできないことを峻別する
変革できることとできないことを峻別する
また、自分が変革できることとできないことを、はっきりと峻別することも大切です。自分が変革できるのは、先のことと自分自身の考え方だけだといえるでしょう。
過ぎ去った過去、起こってしまった事実は変えようもなく、他人の考えも強制的に変えることはできません。自分の力で変革できないことを、いつまでも悔やんで引きずるのは「百害あって一利なし」です。
まったく意味のないことだと割り切り、そのようなことでストレスを蓄積する流れを止めてしまわなければなりません。そしてひたすら、先のことと、より良い考え方に向き合うことが最善策と捉えるべきでしょう。
リフレッシュする手段を持つ
よくいわれることですが、仕事で悩みやストレスあるいは鬱憤などが溜まっていても、オフタイムにはオンタイムのことを完全に忘れるのが有効です。心身をリフレッシュできることがあると、また気力を回復してオンタイムに向き合うエネルギーを補給できます。
趣味やスポーツ、娯楽やボランティアなど、その人に合った何かを持つことが大切です。ともかく、過度の残業や休日出勤を避け、自分の時間を確保して、オフタイムはジムやスパ、サウナなどに行くのもよいでしょう。
読書やゲームに興じるのもよし、ネットで色々なサイトを巡ったりYouTubeなどで動画を楽しんだりの息抜きもよし、とにかく心身ともにリラックスできる時間を作ることが大事です。
転職という選択肢
自分は人を管理する仕事に向いておらず、プレイヤーが向いているということを自覚する場合もあるでしょう。あるいは管理職になることによって、会社の内情を知って幻滅し、違う職場を求める気持ちが芽生えることもあるかもしれません。
さまざまな考え方があり、色々思うことがあっても、もう少しその場所で頑張ってみるというのもひとつの考え方です。しかし、こと心身の健康に関わるくらいのネガティブな状況に陥っていると、無理な我慢はさらに状況を悪化させることになりかねません。
心がパンクしてしまうと、その修復には長い時間を要します。悪くすれば以前のような活気がもうその人に戻ってこないおそれも、充分にあり得るのです。
よって、もう限界かなと感じた場合は、傷を深めないうちに職場を変わるという選択肢が意味を帯びてきます。社内での異動の希望が受け入れられるならそれもよいでしょう。
しかしなかなかそういう希望は通りにくく、また通ったとしてもさまざまな憶測や噂で、新しい部署にも居づらくなるおそれも考えられます。
何もひとつの会社にこだわる必要などなく、他にいくらでも会社は存在するのです。転職を決意したら、一切誰にも他言せずに転職活動を粛々と進めるのがよいでしょう。そして心機一転やり直すことで、新たな活力が湧いてくるはずです。
自分の市場価値を見極めるという意味でも、転職活動は有効な手段になります。気負わずに取り組んでみる中で自分のそれまでやってきたことを棚卸しして、思わぬ発見や発想に至ることもよくあることです。
ひとつの有効な選択肢として、転職を挙げておきます。また、その中で「外資系企業」への転職は違う意味で魅力的です。
外資系企業への転職のメリット
外資系企業は日本企業と比較して、人事評価制度がまったく異なります。具体的なメリットをに確認しておきましょう。
外資系企業で企業の中間管理職事情の昇進は能力次第でスピーディに!
日本企業の場合は、役職に就くまでには能力だけではなく、ある程度の勤続年数も必要です。一方、外資系企業では能力さえ認められれば、中間管理職への昇進に時間などかかりません。
しかも、外資系企業は中間管理職に対する職業評価が高く、日本企業の中間管理職よりもかなり高額な年収が約束されます。
20代でも課長職に相当するマネージャークラスに昇進することもあり、組織そのものが若くてバイタリティに溢れている企業が多いようです。
次に外資系企業に転職する場合を見てみましょう。
外資系企業の中間管理職への転職は肩書き以上のバリュー
外資系企業への転職においては、同じ係長や課長クラスで受け入れられたとしても待遇ははるかに良くなります。
外資系企業にとって年齢はあまり関係がなく能力重視なので、その企業で活躍の舞台があると認められた人材は即戦力として受け入れられるのです。
中間管理職の「つらさ」を日系と外資系で比較
また、日系企業での中間管理職の「つらさ」の部分で外資系と比較し外資系企業てみましょう。への転職で得られるメリットを整理すると下記の通りです。
日系企業:責任がのしかかる割に年収は高くない
↓
外資系企業:責任はのしかかるが、それに見合う年収が期待できる
日系企業:上位者からの理不尽な圧力
↓
外資系企業:フラットな風通しが良い組織で、上位者からの理不尽な圧力がない
日系企業:部下との関係が難しい
↓
外資系企業:個人を尊重するフランクな関係を築ける
昇進のスピードが遅い
↓
昇進のスピードは早い
日系企業:プライベート、家庭内でも問題が出やすい
↓
外資系企業:家庭を大切にする文化の下、家庭をケアできる
年齢に関係なく能力で評価される
昇進に勤続年数は関係がない
年収が大幅にアップする
このように、同じ中間管理職転職でも経験やスキルに自信があれば、外資系企業にチャレンジするでは「つらさ」が大きく緩和され、しかもと年収のアップやグローバルに仕事ができるやりがいなどが待っています。
英語力も含めて、ハードルは決して低くはありません。しかしが、転職で新しく広い舞台を目指してみる価値はあるでしょう。
まとめ
中間管理職のつらさの理由からそれぞれにを探り、対処する方法をご紹介し、また外資系企業の中間管理職とそれを目指した転職について解説しました。日本企業には「しがらみ」や「派閥」などのネガティブな側面も一部ではいまだに存在します。
ある程度頑張ってみることも意味はありますが、無理をして心がパンクしてしまわないうちにしかるべき手を打つことが大切なのはで間違いありません。
現在つらい悩みを抱えている中間管理職のみなさんには、転職という選択肢、なかんずく特に外資系企業への転職という選択肢も視野に入れて、ご自身の人生のビジョンを慎重に、そして前向きに組み立てていただきたいものです。