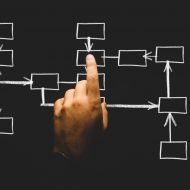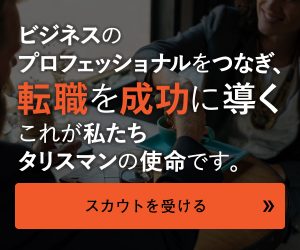ビジネスパーソンとして経験を積み中堅になった人の中には、管理職へのキャリアアップを目指して転職を検討する人も多いですよね。そんな場合には管理職としての適性が自分に備わっているかが気になるのではないでしょうか。
管理職にどういう面が求められるかの漠然としたイメージはあっても、未経験なのでなかなか具体的な資質やスキルはわかりにくい でしょう。しかし、管理職に求められる適性、つまり資質と能力は言語化して表現できます。今回の記事では、管理職に転職する際に求められる適性としての9つのポイントと、それらを磨く方法について解説します。あなたの適性の客観的な把握と、欠けているものを身につけるための参考にしてください。
目次
そもそも管理職とは?
本題に入る前に、まずは管理職とは何かについて、あらためて目を向けておきましょう。
管理職の定義
管理職とは組織において、部署や部門を統括する役職です。担当する現場での、一定の裁量権を持ち、方向性を決める重要なポジションと言えるでしょう。
一般的に管理職と認識される約束は、「部長」「次長」「課長」などがあります。その下位役職になる「係長」や「主任」「チーフ」「班長」「リーダー」などは、管理職の機能の一部を持たされた、管理職の補佐役になります。また、「課長」と「係長」は上層部と現場の中間に位置するので「中間管理職」と呼ばれることもあります。
法律上の管理職とは?
実は企業内での管理職と、法律上の管理職は必ずしも一致しません。労働基準法において管理職を意味する言葉は「監督若しくは管理の地位にある者」=「管理監督者」です。管理監督者は以下の4つの要件をすべて満たす者のことです。
- 企業の一定の部門を統率する立場にある
- 報酬面で十分に優遇されている
- 自身の執務時間や業務量に裁量権がある
- 経営者と一体になって企業経営に関与する
上から3つめまでは、管理職の多くが該当するかもしれません。しかし、役職名だけで部下を持たず給与も勤怠の縛りも平社員並みの「名ばかり管理職」も存在します。また、4つめの「経営者と一体になって企業経営に関与する」に関しては、そうなっていない管理職が多いです。
実際にすべて該当するのは、専務や常務、一部の部長などの経営幹部と言えます。 このように、日常話題になる管理職と法的な管理職にはズレがあることも理解しておきましょう。
外資系企業の管理職との微妙な違い
外資系においては「ディレクター」「マネージャー」などがつくタイトル(職位)が管理職に当たるでしょう。ただし、その下位のスタッフもそれぞれが何らかのスペシャリストとしてタイトルを持ち、その領域に関するある程度の裁量を任されています。
つまり、管理職と部下という日本的な縦の上下関係よりはフラットに近いです。完全なフラットではないにせよ、役割の違いという認識が正しいでしょう。それぞれが担当領域を持って働くスペシャリストをとりまとめ、組織として成果を上げる役割が、外資系の管理職です。
管理職の役割、昔と今の違い
管理職の役割は、昔と今では少々異なります。どんな違いがあるのか、詳しく見ていきましょう。
順風満帆の時代における管理職の役割は「管理」
右肩上がりの時代の日本における企業の管理職の役割は、文字通り部下の「管理」でした。「管理」という言葉が持つ意味は「個々の働きが保てるように全体に気を配って取り仕切ること」です。企業の管理体制は、一般的に社長を頂点にした三角形を描くピラミッド構造になっています。
順風満帆の時代において、企業の中の管理職である部長や課長は、経営陣の意向を部下に伝え、業務を統制する責任を持ちます。管理職の役割は、部下の動きが従来のやり方や決められたルールから逸脱しないように監督することでした。部下の方も同じ仕事を一定の基準から外れず、量をどんどんこなしてさえいれば、確実に業績が向上する時代だからそれでよかったのです。
変化や挑戦の必要など一切なく、決められたことを着実にこなすことだけが求められていました。だからこそ、管理職の部下統率に最適の手法が管理だったのです。
現代における管理職の役割は「マネジメント」
一方、現代の管理職の役割は、組織のリソースを最大限に活かして成果を上げることです。
バブル崩壊やリーマンショックを経て社会の価値観が大きく変化し、デジタル革命で情報格差がなくなった現代はそうはいきません。社会の価値観に応じて変化できない企業は、成長どころか存続さえもできない時代となりました。
そこで注目されたのが、欧米の「マネジメント」の考え方です。「management」の意味は「管理」「監督」も含みますが、他にも「経営」「運営」を意味します。ビジネス上の「マネジメント」は「なんとかやりくりして目標に向かうこと」です。つまりマネージャーは「管理者」「監督者」だけではなく、むしろ「運営者」「経営者」と解釈します。
具体的にいうとマネジメントは、最重要項目である成果を上げるために、効果がありそうな戦略や手法を用いて組織を最善の方法で動かす技術です。また、マネジメントは組織の抱える問題解決の技術という面も持っており、これも管理とは一線を画しています。
このように現代の管理職に求められるマネジメントとは、部下の管理ではなく個々の能力を最大限に発揮させ、戦略的かつ計画的に成果を上げる技術を意味します。
管理職の適性9つのチェックポイントと磨き方
現代においての管理職の役割を解説したところで、本題に入りましょう。現代の管理職はマネジメントができなければなりませんが、それにはさまざまな要素が求められます。そんな管理職の適性として、以下の9つの資質やスキルを備えていることが望ましいでしょう。
- アサーション:他者を傷つけずに主張する力
- コーチング:個々の能力を引き出す力
- ネゴシエーション:交渉する力
- ヒアリング:本音を聞き出す力
- プレゼンテーション:込み入った内容をわかりやすく伝える力
- ファシリテーション:議論を円滑に進める舵取りの力
- リーダーシップ:尊敬と信頼を得る力
- コミュニケーション:良好な関係を構築する力
- マネジメント:組織の能力を引き出す力
これら9つが、管理職の適性としてのチェックポイントとなります。身についていれば良いですが、そうでなければ磨いておくことが必要です。ここからは、9つのチェックポイントのそれぞれの内容と、併せてそれを日頃から磨くための方法や考え方も解説します。
アサーション:他者を傷つけずに主張する力
「アサーション」とは、他者を傷つけない自己主張を意味します。相手の立場をできるだけ尊重しつつ、自らの主張を率直に述べることです。現代の管理職は、成果を上げるために部下を傷つけるようでは失格とされる傾向があります。なぜならかつての組織へのロイヤルティ(忠誠心:日本流にいえば愛社精神)はエンゲージメントに置き換わりつつあるからです。
エンゲージメントは部下の熱意、意欲、仕事への愛着などを意味します。一見似ているロイヤルティは主従関係であり、エンゲージメントは対等な関係です。組織に愛着を持ち、組織への貢献を通して、組織も個人に貢献するのがエンゲージメントのあり方です。
そのため、リーダーとしての確固たる意見を持ちつつも、部下を非難したり誤解させたりすることなく成長をサポートするべきであり、傷つけるのは論外です。そういうマネージャーの振る舞いの根底には、自身の意見を適切に伝えるアサーションが必要です。
アサーションを磨く方法
アサーションは簡単にできることでは決してありませんが、コツをつかめば相手の立場を尊重しながら、自分の意向を伝えることができます。アサーションのコツは、性格を変えるのではなく伝え方を変えることです。それには7つのポイントがあります。
第1のポイントとして、アサーションは自分に正直でなければなりません。自分に正直であるからこそ、気持ちと言葉と行動が一致し、相手に誠実さを伝えることができるのです。
第2のポイントとして、要望を具体的に伝えなければなりません。要望の的を絞って伝え方を工夫することにより、「話したのに伝わっていない」事態を防ぎます。
第3のポイントとして、相手の都合を考えて伝えることです。相手が真剣に聞いてくれるように、時と場所、状況を選んで伝えなければなりません。
第4のポイントとして、相手と同じ目線で話すことです。振る舞いや態度が、上からになってはいけません。実際には立場の上下があったとしても相手を尊重し、人として対等に接することが重要です。
第5のポイントとして、何かを断る場合は相手の気持ちを受け止めてから断らなければなりません。上手な断り方は、まずは相手の気持ちを受け止めて、感謝や労いの意を充分に表明しましょう。その後に状況を素直に述べることで、相手を傷つけずに断ることができます。
第6のポイントとして、自分の価値を信じることです。自分の価値を信じていなければ、相手に自分を信じてもらえなくなります。自分の価値を認識していれば安易な妥協に至らず、最適な解決策にたどり着くことができます。
第7のポイントとして、必ずしもその場で答えを出さないことです。何も言わないほうが良い場合や、いくら考えてもその場で答えが出ない場合もあります。そんな時は相手に、考えをまとめる時間が必要だと伝えましょう。
コーチング:個々の能力を引き出す力
コーチングは個々の部下の、能力や長所を引き出す力です。管理職は成果を上げることに責任を持つのが最も大事ですが、その次に大事なことが部下の成長をサポートすることになります。それを行うためにはコーチングの力が必要です。コーチングによって、部下との普段の何気ない質問からでも、その人の能力を発揮させるきっかけを作ることができます。
コーチングを磨く方法
コーチングを磨くためには、3種類の基本的な質問の仕方をマスターしましょう。
1つめは「引き出す問いかけ」です。多くのプロフェッショナルのコーチがコーチングで行う「質問」は、この引き出す質問でしょう。相手から何を引き出すのか以下の要素です。
- 現状の認識
- ゴールと考えているもの
この2つが最重要です。それを補足する意味で以下の要素も引き出せるとなおよいでしょう。
- セルフイメージ
- 自分のルール
- 信念
- 価値観
具体的な質問の仕方の例は以下のとおりです。
「あなたにとって〇〇は何を意味しますか?」
「なぜ〇〇がそんなに大切なのですか?」
「〇〇を希望する理由は何でしょうか?」
そして引き出した情報を活用し、相手に「気づき」を与えることができます。また、現状のままだと何を失うのか、変化することで何が得られるのかなどを考えさせることが可能です。
2つめの質問は「状態の確認」です。「引き出す質問」をしても反応が良くない場合は、質問の仕方に問題があるのではなく、タイミングが合っていないと考えて良いでしょう。「価値観」や「信念」などの深い内容は、普通の生活で常に意識 しませんよね。だからそれを引き出すには、相手が良い状態にしましょう。そのため、相手の状態や頭の中を何が占めているかを、チェックする必要があります。実践では以下のような質問をしましょう。
「今はどのような気分ですか?」
「今、何のことを考えていますか?」
このような質問によって、相手の反応を確認しながら、「引き出す質問」を進められる状態かどうかを見極めましょう。
3つめの質問は「モチベーション」です。これには、「引き出す問いかけ」で相手から引き出せた「現状」と「ゴール」を材料にします。
「なぜ、そのようなゴールに辿り着きたいのですか?」
「ゴールに辿り着くことで得られるものは何なのか?」
相手の中でそれを言葉にすることで考えが整理でき、ゴールがより具体的になります。相手が前向きな精神状態であれば行動の動機付け、つまりモチベーションとなる可能性が高まります。
ネゴシエーション:交渉する力
ネゴシエーションは、交渉を有利に進めるための力です。
これは部下との交渉ではなく、部署が持つ取引先や関係するステークホルダーとの交渉であり、時としては部署を代表して部下のために経営陣と交渉することもあるでしょう。交渉相手の立場に合わせ、交渉の仕方を身につけることが必要です。相手の要求を正しく理解するために、最優先のニーズを見極め、それに照準を合わせた提案をしなければなりません。
ネゴシエーションを磨く方法
ネゴシエーションの力を普段から磨くために、以下の3種類の思考を習慣づけましょう。
- 自分の客観視
- 交渉相手の観察
- 妥協点の発見
それぞれを見ていきましょう。
【自分の客観視】
交渉では逆境に立たされることや、あとひと息で交渉が成立しそうになるなどさまざまな局面があります。自分を客観視することは、交渉で役に立ちます。なぜならどのような局面でも感情に流されることなく、冷静な判断ができるからです。焦りや自信過剰は、足元が不安定になります。自分の状態と言動を常に客観視する訓練を積みましょう。
【交渉相手の観察】
交渉相手を深く観察し、要求や関心がある対象を知ろうとする訓練は交渉に役立ちます。交渉の基本はWin-Winなので、相手に得るところがなければどこまでいってもまとまりません。自分の要求を伝える以上に、相手が本当に求めているポイントを的確に察知する必要があります。それは言葉としてはっきり出てくることよりも、むしろ表情や仕草、沈黙のタイミングなどが暗示する場合も多いです。
そういう微妙なサインから相手の本当の要望や不満を知れば、相手の心を動かす提案がしやすくなります。そして、交渉が成功する可能性も高まります。
【妥協点の発見】
ネゴシエーションの最終目標は、双方が納得いく妥協点に至ることです。交渉のプロセスも大切ですが、完結させるには妥協点を見つけなければなりません。限られた条件の下で、双方にとって得るものがある妥協点を発見する努力こそ、ネゴシエーションの力を磨く最大の訓練です。
ヒアリング
管理職は周りの人たちを良く理解し、自分と異なる意見も受け入れるキャパシティが必要です。そのためヒアリングによって、他者に対し真摯に傾聴することが大切となります。
誰しもが本来、自分の話を聞いてもらいたいという願望を持っています。相手の話をさえぎることなく、相槌を時には打ちつつしっかりと相手の意見を受け止めることは、深い信頼関係を構築する上で有効です。
ヒアリングを磨く方法
ヒアリングが上手になるためには、普段から会話の中で5W1Hを意識することが効果的です。もちろん、必ずしも5W1Hのすべての項目をヒアリングする必要はありません。話の内容や流れに応じて、適度に絡めると効果的です。
会話の中で「それは誰でしょうか」「なぜそれを選んだのでしょう」「どのように決めたのでしょうか」などを適宜はさみこみましょう。それによって、相手の中で考えが整理されていき、話の本質に迫ることができます。
また、クローズドクエスチョンとオープンクエスチョンを使い分けると、情報を引き出しやすくなります。前者は答えが二者択一などに限定される質問の仕方で、後者は自由な答え方ができる質問の仕方です。相手の意思や方向性の確認はクローズドクエスチョン、多くの情報を引き出したいときはオープンクエスチョンと使い分けていきましょう。
いずれかに決めてもらうクローズドクエスチョンは、相手の意思や志向性を確認するのに役立ちます。相手が自由に答えられるオープンクエスチョンは、幅広い答えを引き出すことができます。例えば以下のような質問の仕方です。
クローズドクエスチョン:あなたの価値観に合うのはAとBのどちらでしょうか?
オープンクエスチョン:あなたはどういう価値観をもってこの問題を考えますか?
プレゼンテーション
プレゼンテーションの力の発揮場所は、必ずしも業務としてのプレゼンに限定されません。部下や取引先などの第三者に伝えたいことをわかりやすく伝えて、行動に移してもらうために常に役立ちます。部署の活動や取引関係を望ましい方向に、スムーズに向かわせることができるでしょう。
プレゼンテーションを磨く方法
プレゼンテーションの力を普段から磨くためには、「目的とゴールの明確化」「聞き手の属性の理解」「話し方に配慮」「体全体で表現」という4つのことを心掛けましょう。「目的とゴールの明確化」は、目的を明らかにして何を伝え、どういう行動を起こして欲しいのかをはっきりと決めることです。
「聞き手の属性の理解」は、聞き手に「共感」を与えるために役立ちます。属性を知れば聞き手の視点に寄り添った伝え方や、伝える項目を調整することも可能です。聞き手の共感が得られると、そのプレゼンや伝達はすでに成功と言えるでしょう。
「話し方に配慮」は、話し方ひとつで説得力は変わるということです。特に声の大きさや語るスピード、話の間などが大切です。専門用語を使うならゆっくりはっきりと話し、話の方向性が変わる時はちょっと間を空けるなど、聞き手が理解しやすいよう配慮しましょう。
「体全体で表現」は、話の中で特に強調したい内容に関して、全身で伝えるイメージで話すことです。声を張り、身振り手振り、表情も交えて表現します。常にそうだと違和感を与えるので、ここぞというタイミングで活用する訓練をしましょう。
ファシリテーション
ファシリテーションとは会議の舵取りをする能力です。本質的には組織活動が円滑に進むようコントロールする力と言えるでしょう。
ファシリテーションは社内や取引先との会議で、参加者が忌憚のない意見を発信しやすい場を作ります。また、各人の意見を尊重しつつ課題を特定し、議論を進める環境を生み出すでしょう。あるいは、タイミングがつかめず議論に加われない人に水を向け、巻き込んでいきます。会議が円滑に進み、有益な結論に到達させられるファシリテーションを管理職は持つべきでしょう。
ファシリテーションを磨く方法
ファシリテーションを普段から磨くために、以下に挙げるような項目を意識しましょう。
まず、若手社員や役職がない社員は立場上、会議で発言しにくいケースがあるでしょう。しかしそういう立場だからこそ可能な発言の仕方もあります。例えば発言の冒頭に「私の理解が正しいかかどうか、確認させてください」と謙虚に述べてから自分の意見を述べるだけで、役職者と違う視点での発言が可能になります。
また、会議にまとまりがない時に見落とされがちなのは、決定していないけれど重要な項目です。それらを再び話題に据えることで、徐々に全方位的に網羅された議論に導けるようになります。他には、会議の終盤でも決まらないことについて、流される場合が多いものです。それを流さずに、誰がいつ詰めるのかなどを明確に確認すれば、議論の抜け漏れをなくし、会議に一貫性を与えられます。
リーダーシップ
部署や部門の目標は、多数のメンバーが参加するチームで進めていくものです。そのため管理職は、チームメンバーと向き合うあらゆる場面でリーダーシップが求められます。
部下にとって管理職にリーダーシップが感じられなければ、どうなるでしょう。表面的には従っても、本心から敬意を払っていないので、求心力が弱くなります。管理職に強いリーダーシップがあってこそ、助言や指導が部下に素直に受け入れられ、良いチームとなるでしょう。
リーダーシップを磨く方法
リーダーシップを日頃から磨く訓練として「自ら声をかける」「他者から学ぶ」「第三の策を準備する」の3つがあります。
「自ら声をかける」は、かつてのリーダー像ではありません。リーダーから声をかけるのは自分を安く見せるという価値観の人が多かったからです。しかし、現代のリーダーは自分から声をかけることが大切です。自分から気軽に挨拶をし、部下の体調が悪そうだと感じれば気遣う、当たり前のことを気負わず実行するのが現代のリーダーと言えるでしょう。
「他者から学ぶ」はリーダーの基本です。歴史上の成功者と言われる人達は、先人からはもちろん、周りの人からも謙虚に学ぼうとする人が多く見られます。だからこそリーダーとしての度量も大きくなるのでしょう。「第三の策を準備する」は、優れたリーダーの特徴です。最善策も次善策も効果がない局面を想定し、第三の策でリスクを回避しつつ仕事を着地させる準備を常にしておきましょう。
コミュニケーション
コミュニケーションの能力は部下を率いて仕事をする、あらゆる人に必要です。部下もそれぞれ個性があり、人数が多くなればどうしても相性の問題が出てきます。
管理職が各人の個性を見極め、組織を上手にまとめることにより、全員が同じ方向に向かって嬉々として仕事に取り組めます。そういう環境を作れるかどうかは、管理職のコミュニケーションに依るところが大きいです。
コミュニケーションを磨く方法
コミュニケーションの力を磨くために普段からできる訓練として「ノンバーバル」「ペーシング」「アクナレッジメント」を実践しましょう。
「ノンバーバル」は口調や表情、身振り手振りなどの言葉以外の部分で伝えるコミュニケーションです。ノンバーバルは言葉以上のものを伝えることがあり、話しやすい雰囲気を作ることができます。これを意識すればコミュニケーションレベルは深くなるでしょう。
「ペーシング」は相手に安心感を与えるために、あえて相手に合わせた言動を取るテクニックです。人は他者との違いに不安を感じる一方で、共通することに安心を感じます。そのため、話題や表情、使う表現や話すテンポ、注文する品名などを相手に寄せると緊張を和らげることが可能です。その結果、より深い対話が可能になります。
「アクナレッジメント」とは、相手の存在や能力、努力などを評価し、それを伝えることです。相手の存在価値を認めることで承認欲求を満たしてあげることができ、信頼関係を深めるのに役立ちます。
マネジメント
マネジメントの力は、管理職が備えるべきさまざまな資質からなる、総合的な能力とも言えるでしょう。マネジメントの構成要素を分解すると「現状分析」「問題解決」「計画推進」「意思決定」の4つとなります。
「現状分析」は組織の状態を理解し、課題を的確に把握することです。これが欠けていると適切な指示が部下に出せません。
「問題解決」は現状で何をすれば問題を解決できるのかを、的確に判断する力です。経験や勘に頼らず、論理的に問題を解決に導く必要があります。
「計画推進」は、計画を進めるための最善のロードマップを立てて、ゴールまでプロセスをコントロールする力です。細部を把握し全体を俯瞰するという両極の行動を常に求められます。
「意思決定」は危機に直面した場合においてもブレない軸を持ち、柔軟に判断する力です。不透明な状況でも管理職が揺るぎない意思で的確な判断を下せば、部下も信頼してついてきます。
マネジメントを磨く方法
マネジメントの力を日頃から磨くためには、相手の視点に立ってみる「ポジションチェンジ」を実践しましょう。
部下の視点、取引先の視点、経営者の視点、エンドユーザーの視点などに自分を置いてみるとそれまで見えなかった要素や課題が見えてきて、解決の糸口が見つかることが多いです。
欠けている部分を補うアクションを起こそう
管理職の適性に関してのチェックポイントを9つ紹介しました。
最初からすべて備わっている人など稀でしょう。大切なことは、自分に欠けている部分を客観的に認識し、それを磨いていこうとアクションを起こすことです。転職活動中にそれらを身につけるに至らないとしても、それが必要だと自覚して身につける努力を継続しましょう。そのプロセスを積極的にアピールすることで、選考担当者によい印象を与える可能性が高まります。
身につけるために自分でできる日頃の取り組みは、すでに各チェックポイントで述べたとおりです。ここでは、外部の力を借りてできる取り組み方法を紹介します。
まず、欠けている資質に関する書籍を読むことで、学べることがたくさんあるでしょう。ここで挙げた9つのポイントのそれぞれをテーマとしてフォーカスした書籍が、たくさんあるはずです。次に、セミナーを活用するのも良い方法です。費用はかかりますが、テーマが絞り込まれたセミナーの受講を通して具体性を伴った学びができます。最後に、転職エージェントに相談すれば、あなたのキャリアとスキルの棚卸しやヒアリングを通して、管理職としての適性について真摯な助言が得られるでしょう。実際に転職活動のさまざまな面をサポートしてくれるので、利用しない手はありません。
タリスマンは外資系とIT業界に強く、管理職などのハイクラス求人を多く扱う転職エージェントです。あなたのふさわしい管理職の求人を最大限にサポートします。「いますぐ求人を探す」ボタン、あるいは「タリスマンに転職相談をする」ボタンを押して、タリスマンとともに管理職への転職に向けて、最初の第一歩を踏み出しましょう。
まとめ
管理職に転職する際に求められる適性のチェックポイントと、それらを磨く方法について紹介しました。客観的に自分の適性を見極め、管理職の仕事をするために欠けているものを磨くアクションを、直ちに起こすのが賢明です。
日頃からできる方法や外部の力を借りて磨く方法、転職エージェントの活用などを通して管理職としての適性をできるかぎり磨き上げ、転職に成功しましょう。